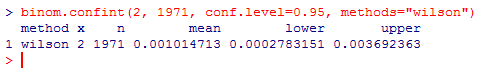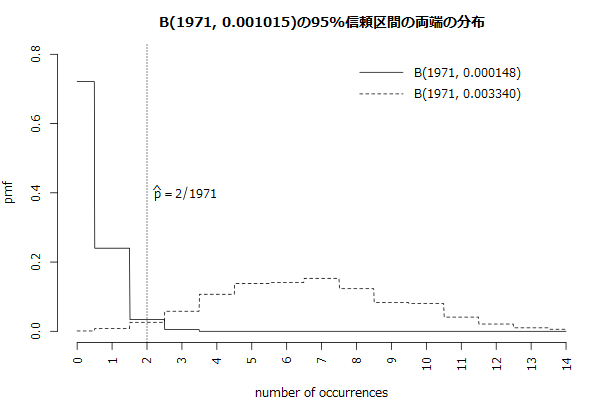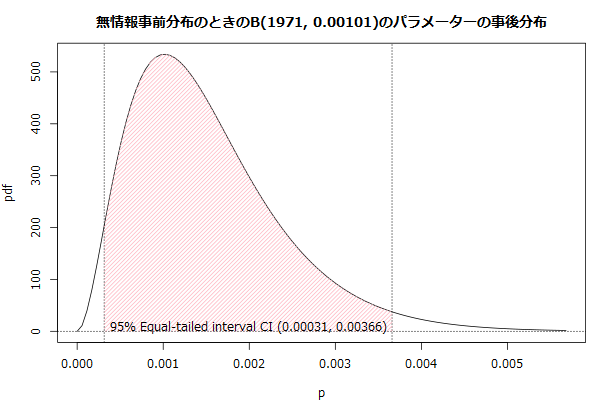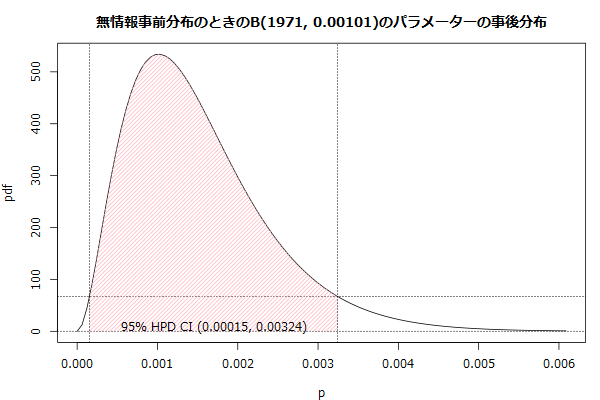数値解析における数値積分法の代表としてガウス求積と言う技法があり、それに必要なガウス点と重みの計算でJuliaがC++より桁違いに速いと言う話が流れていたのですが、Juliaで使われているFastGaussQuadrature.jlが使っているアルゴリズムのC++版を使ったところ、案の定、だいたい同じの速度になりました。
Fast computation of Gauss-Legendre Quadrature Points and Weights(FASTGL)のアルゴリズム開発者のページからfastgl.cppとfastgl.hppをダウンロードしてきて、積分に使うだけです。サブディレクトリfastglにこの2つのファイルを配置したところで、以下のソースコードのファイルを作成してコンパイルしたら簡単に実行できます。-O3 -lmオプションはいると思いますが。
#include <iostream>
#include <chrono>
#include <iomanip>
#include <functional>
#include "fastgl/fastgl.hpp"/*
FASTGLを使って積分をする関数
args: ラムダ関数f(x), xの最小値, xの最大値, 節点の数
*/
double integral(std::function<double(double)> f, double s, double e, int NumberOfKnots){
double Res = 0.0;
double xm = 0.5 * (s + e);
double xr = 0.5 * (e - s);for ( int k = 1 ; k <= NumberOfKnots ; ++k ){
fastgl::QuadPair p = fastgl::GLPair ( NumberOfKnots, k );
Res += p.weight * f( xm + xr * p.x());
}return Res*xr;
}int main(){
std::chrono::system_clock::time_point stime, etime;
stime = std::chrono::system_clock::now();// boost::math::quadratureあたりと異なり、節点が100万個でも大した時間にならない
double Res = integral([](const double& t) { return 1.0 / 2 / std::sqrt(t); }, 1, 4, 1000000);etime = std::chrono::system_clock::now();
std::cout << std::setprecision(16);
std::cout << "Results: " << Res << std::endl;
std::cout << "Elapsted Time: " << std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(etime - stime).count() << " ms" << std::endl;return 0;
}